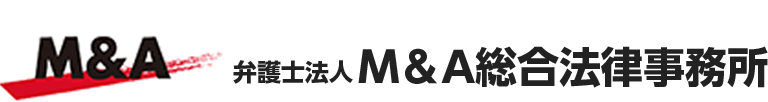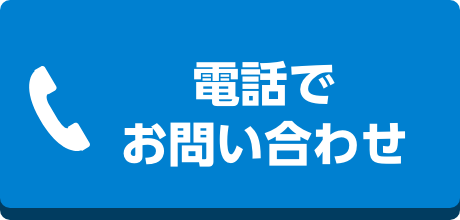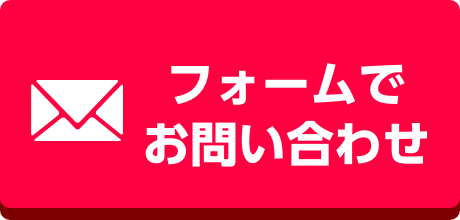役員退職慰労金不支給・不当不再任に伴い生ずる問題とは

会社の代表取締役・取締役や監査役へ支払うべき役員退職慰労金は、株主総会の決議により金額を決定するのが原則なので、株主総会の決議がなされなければ、役員退職慰労金は支給されません。しかし、使用人兼取締役の場合は、使用人分については株主総会の決議の有無に関わらず、退職慰労金を支給すべきこともあります。
役員退職慰労金の不当不支給、不当不再任の事例では、裁判が提起される等、大きなトラブルになることもあります。
そのため、M&Aの法務デューデリジェンスにおいて、代表取締役・取締役や監査役に対する役員退職慰労金の支給義務が存在していないかを検討することは非常に重要です。
役員退職慰労金は株主総会での決議により支給が決まる
会社法361条1項の規定により、代表取締役や取締役に対する報酬等については、定款で額を決めていない場合は、株主総会の普通決議で決めることになっています(監査役も同様)。
この報酬等は、月額の報酬の他、「賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益」を意味するため、「役員退職慰労金」も含まれます(最判昭和39年12月11日 民集 第18巻10号2143頁)。
役員の報酬等について、定款又は株主総会の決議事項としたのは、取締役によるお手盛りの弊害を防止し、株主の利益を守ることが目的です。
役員退職慰労金について、定款に定めがある会社はあまりありません。
そのため、役員退職慰労金は、株主総会での決議がなければ、支給されないのが一般的です。
役員退職慰労金をもらう旨の黙示の特約があった場合
取締役が就任するにあたって、会社との間で役員退職慰労金をもらう旨の黙示の特約を結んでいた場合でも、それだけでは、退職時に役員退職慰労金を請求することはできません。
最高裁も、株式会社の取締役については定款又は株主総会の決議によって報酬の金額が定められなければ、「具体的な請求権」は発生せず、取締役が会社に対して報酬を請求することはできないとしています(最判平成15年2月21日 金判1180号29頁)。
そして、定款又は株主総会の決議なしで、取締役が報酬を受け取った場合は、不当利得となるため、会社へ返還しなければならないのが原則です(最判平成21年12月18日 集民 第232号803頁)。
もっとも、この判例は同時に、会社が取締役に対して不当利得返還請求をすることが信義則に反し、権利の濫用に当たる場合もある旨を示唆しています。
使用人兼務取締役の使用人分の退職慰労金
取締役は、会社の経営者であると同時に使用人つまり、従業員でもあるケースも少なくありません。
従業員が受け取る退職慰労金については、定款又は株主総会の決議は必要ありません。
一方、使用人兼務取締役が受け取る退職慰労金については、従業員にも共通に適用される退職慰労金支給規定において勤続年数と退職時の報酬日額を基礎にして算出されるものであったとしても、会社法361条1項の規定により、定款又は株主総会の決議によって金額を決めるものとされています(最判昭和56年5月11日 集民 第133号1頁)。
もっとも、これにも例外があります。
最高裁は、「使用人として受ける給与の体系が明確に確立されており、かつ、使用人として受ける給与がそれにより支給されている」なら、使用人分を除外したうえで、取締役として受け取る分についてのみ株主総会の決議によることができるとしています。このことは、会社法361条1項の脱法にも当たらないと解しています(最判昭和60年3月26日 集民 第144号247頁)。
つまり、使用人兼取締役に対する退職慰労金は、使用人分と取締役の分が明確に区分されているなら、使用人分については、定款又は株主総会の決議がなくても支払わなければならないということです。
いったん決まった退職慰労金を無報酬、減額することの可否
取締役の退職慰労金について、株主総会で具体的な金額が決定された場合は、その金額は会社と取締役の契約内容になります。
では、その後で、株主総会が金額について無報酬とする決議や減額する決議をした場合はどうでしょうか?
最高裁は、上記の契約が成立した以上は、契約当事者である会社と取締役の双方を拘束するため、取締役が同意しない限り、退職慰労金請求権を無報酬としたり減額することはできないとしています(最判平成4年12月18日 民集 第46巻9号3006頁、最判平成22年3月16日集民 第233号217頁)。
取締役の職務内容に著しい変更があった場合、社会経済情勢等が変化した場合、将来退任する取締役との間に不公平が生じるおそれがある場合でも同様です。
M&Aにおける役員退職慰労金不支給のリスクとは?
M&Aでは、相手方の会社の代表取締役・取締役や監査役を退任させる場合に、役員退職慰労金を支払う必要があるのかどうかが問題となります。
定款の定め又は株主総会の決議があった場合は、支払う必要がありますが、そうでなければ、代表取締役・取締役や監査役の役員退職慰労金などは無視してかまわないという考え方が蔓延しているようです。
ただ、代表取締役・取締役や監査役といっても、必ずしも、会社経営者というわけではなく、ほとんど従業員と同じであり、ほとんど労働基準法を適用すべき代表取締役・取締役や監査役も存在しますし、役員退職慰労金を支給しないことが合理的とは言えない代表取締役・取締役や監査役も存在します。
役員退職慰労金の不当不支給については支払命令が出る場合もある
こういう事情を考慮して、近時では、代表取締役・取締役や監査役が役員退職慰労金の支給を求めて会社を訴える事例も増加しており、そのような事例で実際に、会社に対して、代表取締役・取締役や監査役への役員退職慰労金の支給を命じる判決も出てきています。
従業員への退職金の不当不支給では、会社が敗訴する可能性が高いです。
そのため、代表取締役・取締役や監査役であっても、雇われ社長など、従業員と大きく取り扱いを変えることはおかしいのではないかという考えが発生することは自然と言えます。
また、不祥事や懲戒事由に基づき辞任した代表取締役・取締役や監査役について、役員退職慰労金の支給を実施しないことは、必ずしも正当と言えない場合もあり、このような代表取締役・取締役や監査役から会社に対して、退職慰労金の支給を請求し、裁判所から役員退職慰労金の支給を命じられるケースも存在します。
更に、会社の内規により、役員退職慰労金の支給を前提とする議案が株主総会に速やかに提出されて可決されるものだと、退任取締役が強い期待を抱いていた場合に、役員退職慰労金を不支給とする議案を提出して可決させた取締役会の措置につき、退任取締役の期待を裏切り、人格的利益を侵害した違法なものであるとして、退任取締役に対する不法行為に当たると判断した判例もあります(大阪高判平成19年3月30日)。
こうしたことから、M&Aの法務デューデリジェンスにおいて、代表取締役・取締役や監査役に対する役員退職慰労金の支給義務が存在していないかを検討することは非常に重要になっています。
役員の不当不再任についても訴えられるケースが増えている
また、代表取締役・取締役や監査役についても、任期満了で再任しなかった場合、それを不当だとして、代表取締役・取締役や監査役が裁判所に訴えを提起することも多くなっています。
従業員の不当解雇は会社が敗訴する可能性が高いです。
そのため、代表取締役・取締役や監査役であっても、雇われ社長など、従業員と大きく取り扱いを変えることはおかしいのではないかという考えが発生することは自然と言えます。
従業員の場合、不当解雇の場合は、解雇無効になりますし、解雇無効となり職場復帰するまでの給与もさかのぼって支給しなければいけません(バックペイ)。
代表取締役・取締役や監査役が解任された場合も、会社法339条2項により、「その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされています。
そして、この損害賠償額は、残存任期分の役員報酬額はもちろん、任期満了時に支払われていたであろう退職一時金に相当する額も含むと解されています(東京地判平成29年1月26日)。
代表取締役・取締役や監査役の不当不再任でなく、辞任であったとしても、必ずしも、自由意思による辞任でない場合については、同じ問題が発生します。
こうした点においても、M&Aの法務デューデリジェンスでは、代表取締役・取締役や監査役に対する不当不再任となっていないか、不当不再任であり、代表取締役・取締役や監査役を遡って再任する必要がないか、遡って役員報酬を支給する必要がないか、を検討することが重要になっています。